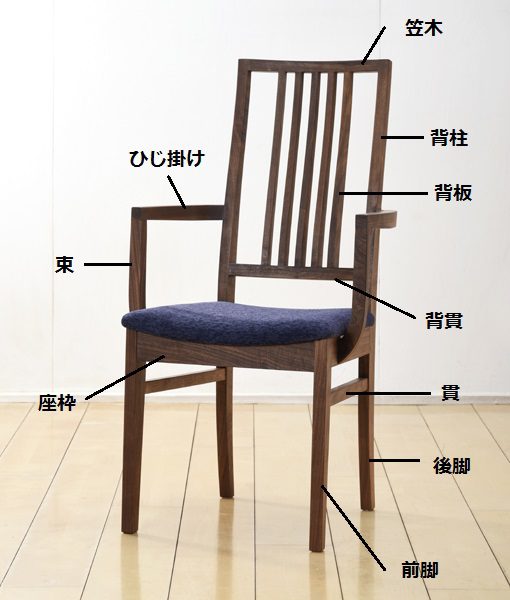チェストやタンスの引出しには様々な開閉方法があるのをご存知ですか?
同じような引出しに見えても実は少しずつ違うんです。
大きく分けるとレールがあるか、ないか。
レールの有無による違い、引出し方によって何が変わるのか、それぞれの特徴をご紹介します。
<レールがないタイプ>

所謂、片方の引出しを閉めると片方が開いてくるというような職人の技が光るレールがないタイプです。
寸分違わぬ正確さで作られた上質な引出しは空気の逃げ場がなく、片方の引出しを押し込んだ時に一緒に押し込まれた空気が、もう片方の引出しを押し出すのです。
一番オーソドックスな工法で、チェストやタンスといえば大昔からこの方法で作られてます。
■メリット
・レールを使用しなので、不具合が起きる可能性がない。
・レール分の寸法が必要ないので、内寸をできるだけ大きくとれる。
■デメリット
・重量のあるものや量のあるものを仕舞うと、開閉が重くなる。
<レールがあるタイプ>

レールによる開閉補助を行い、プッシュオープンやスロークロージングなどさまざまなタイプがあります。
チェストの歴史の中ではごく最近生まれた作りですが、近年の技術向上などによりとても使いやすい商品がたくさんあります。
■メリット
・重量のあるものを仕舞っても開閉が楽に行える。
・開閉補助機能付きタイプなど種類も様々あり、使途に応じて使い分けられる。
・種類によってはフルオープン(内箱を全開に引き出せる)もあり、奥のものも取り出しやすい。
■デメリット
・レールの不具合、消耗の可能性があるため、交換が必要となる場合がある。
<どちらが良いの?>
選択肢があると人はどちらか良いほうを選びたいものです。
結局どちらが『良い』かと問われれば、どちらも『良い』のですが、
前述したようにどちらにも『良い』面と『悪い』面があります。
つまり全ては使いどころなんです。
こちらのチェストご覧ください。

上の二段はレールがなく、下の一段だけレールがあります。
こうなっているのには二つの理由があります。
まず最下段の引出しは容量が大きく、仕舞うものが増えるといずれ重量がますでしょう。そうなるとレールによる開閉補助が役に立ちます。
また、上の二段はカトラリーなどを仕舞う小さめの引出しであり、ここにレールを付けると内寸に大きな影響が出て仕舞います。
さらに仕舞える量が限られているので、レールがなくても大丈夫なんですね。
このようにひとつの商品の中でも使い分けがなされているのです。
どちらの作り方にもメリット・デメリットがありますので、すべては適材適所がポイントです。
<番外編>
ほとんどのチェストやタンスは上記のような作り方で作られていますが、
最後にちょっと変わり種をお紹介します。

こちらのチェスト。非常に作りがきれいで人気の商品なんですが、レールに注目してみてください。

上でご紹介した作りとはまた異なった形状をしています。
内箱を掘り込み、木のレール上をスライドさせるような作りで、金属製のレールともレールのないタイプともまた違った『開け心地』があります。
今後引出しのある収納をお考えの際は、レールについてもひとつご一考下さい。